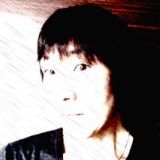芸術運営論I:基礎概論
1958年徳島県生。早稲田大学大学院修了(都市計画)後、社会工学研究所などを経て1989年から現職。東京オペラシティ、国立新美術館、いわきアリオス等の文化施設開発、東京国際フォーラムのアートワーク計画などのコンサルタントとして活躍する他、文化政策、文化施設の運営・評価、創造都市等の調査研究に取り組む。文化審議会文化政策部会委員、東京芸術文化評議会専門委員、(公社)企業メセナ協議会理事などを歴任。著作に「再考、文化政策(ニッセイ基礎研所報)」「アート戦略都市(監修、鹿島出版会)」など。