(※2025年11月6日修正)
7月20日(日)に開催された音楽環境創造科・学科説明会のアーカイブ動画をご覧いただけます。
詳細は学科説明会のページよりご確認ください。

このQ&Aは、説明会当日の質疑応答と、事前に寄せられた質問の概要をまとめたものです。
Q.外国人の研究計画発表で注意すべき点は何ですか?留学生は研究生を経ずに直接修士課程の入試を受けることは可能ですか?
A.修士課程の入学試験については、応募要項に記載の条件を満たしている方であればどなたでも受験可能です。
Q.音楽音響創造研究分野ではどのようなことを主なテーマとして研究しているのか。
A.過去に提出された修士論文の題目一覧と概要が学科ホームページに掲載されています。また、修士論文の本文は音環教員室で閲覧可能です。事前予約が必要なため、メール等で訪問希望日時をご相談ください。また、博士論文については大学図書館HPのリポジトリで公開されています。毎年12月の千住アートパスや、2月の卒展でも学生による発表を一般公開していますので、ぜひご来場ください。
Q.試聴試験の対策について、音圧レベルの判定の問題はどのように対策すればよいでしょうか?
A.自身がお使いの音楽ソフトウェアを用いて、レベルやEQの変化を実感してみてください。実技ですので、繰り返しの練習をおすすめします。
Q.社会人の受け入れは可能でしょうか?
A.可能です。ただし、学生個人ごとの研究対象に応じて異なります。修士課程では2年目の12月に論文を提出する必要がありますので、研究のペースは速く、忙しく過ごすことになります。
Q.他大学からの進学者はどれくらいいるかお尋ねしたいです。
A.入学年度によって比率は異なりますが、過去5年間では45%が音楽環境創造科以外からの入学でした。
Q.事前提出物について:研究計画書と必ず関連する必要がありますか?
A.基本的には修士課程で研究ができるかどうかを見ています。まったく関係がない作品がきても研究の能力・準備状況について判断できないので、関係のあるものが望ましいです。学科HPから過去の修士論文を見てもらえるとわかりやすいかと思います。
Q.入学後に研究テーマを変えることは可能ですか?
A.研究計画書によって当研究科で研究できるものかどうか判断しているので、マイナーチェンジはあってもメジャーチェンジはないと考えていただければと思います。
Q.服飾の大学出身なのですが入学できますか?
A.入試では出身がどこかということは関係なく、研究する準備が整っているかどうかを判断します。また、修士課程は最長3年しか在籍できないので、その年数で研究がしきれるかというところも大切です。
Q.研究生をした後に修士課程に行きたいと考えています。研究生と修士課程の違いを教えてください。
A.研究生は研究をするのが主目的の学生で、単位を取得することはできません(ただし、教員の許可があれば授業の聴講は可能です)。非正規生のため、学割を使えなかったり、メールアドレスのドメインが違ったりと細かな部分でも違いがあります。また、卒業の際に「修士」などの資格を得ることはできません。

7月13日(土)に開催された音楽環境創造科・学科説明会のアーカイブ動画を期間限定で公開いたします。視聴をご希望の方は、下記のGoogleフォームに必要事項をご入力ください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にアーカイブ動画のURLをお送りいたします。ご入力内容にお間違えのないよう、お願い致します。
視聴申込の〆切は2024年8月30日(金)18時まで、
アーカイブ動画の視聴期限は2024年9月1日(日)までです。

このQ&Aは、説明会当日の質疑応答と、事前に寄せられた質問の概要をまとめたものです。
Q.入試の過去問に音響学についての知識を問う設問がありますが、対策に有効な音響学の書籍はありますか。
A.音響学のごく初歩を説明する書籍であれば足りるかと思います。具体的には小泉宣夫「基礎 音響・オーディオ学」(コロナ社)、日本音響学会 編「音響学入門」(コロナ社)など、広い範囲をカバーしたものがよいでしょう。また、過去問を参考にして自身に必要な知識を考えてください。
Q.修士論文と作品の組み合わせで卒業する場合、作品はどの程度成績評価の対象となりますか。作品が評価の対象となる研究分野はどこですか。
A音楽音響創造研究分野の修士課程では、論文に作品を添付することができますが、修士論文が評価の対象になります。
Q.修士課程への願書提出にあたって、どんな書類と作品を準備しなければなりませんか。作品に対する要望はありますか。そして作品はどうやって提出すればよいでしょうか。
A.募集要項をご参照ください。特に要望はありませんが、修士、博士の2年間・3年間で達成できるものか、また、大学院における研究としての意義があるものかなどが問われます。
Q.ECMジャズやバロック、ルネサンス音楽を中心にして研究しています。大学では古楽器(リュート、チェンバロなど)での研究ができますか。
A.「古楽器での研究」がどのような研究形態か分かりませんが、少なくとも音楽音響創造分野では、楽器演奏技術の指導は行っていません。
Q.研究室の訪問はするべきでしょうか。
A.必ず訪問するべきということはないですが、研究テーマがここの研究室で達成できるものかどうかなど不安があれば、音楽環境創造科教員室経由で質問メールをしていただいて構いません。必要な場合は早めに、少なくとも願書を出すよりも前にご連絡ください。基本的にはメールで回答しますが、実際に会う必要がある場合は訪問していただくこともあるかもしれません。
Q.学生の履修スケジュール等、大学院での研究ペースや過ごし方のイメージについて教えてください。
A.学生個人ごとの研究対象に応じて異なりますが、修士課程では2年目の12月に論文を提出する必要がありますので、研究のペースは速く、忙しく過ごすことになります。
Q.どの研究室で研究すべきか定まっていない場合、入ってから研究室を決めたり横断して研究することはできますか。
A.たとえば修士の場合、入って2年で修士論文を書き終えることになるので、研究内容は入る段階でしっかりと定まっている必要があります。ただし別の研究室の先生にも研究について相談することは可能です。
Q.研究生の受け入れ人数は決まっていますか。
A.人数は決まっていません。一定のレベルを満たしているかどうかや、希望の研究室が人数などの都合上研究生受け入れ可能であるかなどによって検討します。
Q.提出作品の音楽ジャンルに制限はありますか。
A.録音:特に制限はありません。どういう観点、どういう条件で録音・ミックスしたものかがきちんと書かれていれば良いです。
創作:特に制限はありませんが、音楽音響研究分野で研究・制作する意味、誰が審査するのかをよく考えてください。
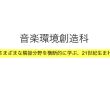
7月16日(日)に開催された音楽環境創造科・学科説明会のアーカイブ動画を、期間限定で公開致します。視聴をご希望の方は、下記のGoogleフォームに必要事項をご入力ください。
ご入力いただいたメールアドレス宛にアーカイブ動画のURLをお送りいたします。ご入力内容にお間違えのないよう、お願い致します。
アーカイブ動画の視聴期限は2023年8月31日(木)までです。

このQ&Aは、説明会当日の質疑応答と、事前に寄せられた質問の概要をまとめたものです。
Q. 科目履修生はとっていますか?
A. 「科目等履修生」は、(1)本学部卒業者で教員免許あるいは学芸員資格取得を希望する者、(2)職場から派遣される者、(3)高校卒業以上の外国人、に受験資格があります。受講できる科目は指定されたクラス授業に限ります(科目一覧表が募集要項に入っています)。
Q. 総合大学の学生です。修士課程の受験をしようと勉強をしていますが主な試験対策について伺いたいです。
A. 過去の問題が公開されていますので、参考にして下さい。
Q. 研究生のコースと大学院コースの具体的な違いは何ですか?研究生で大学院受験対策コースはありますか?研究生でコースを選択することは可能ですか?たとえば、高度な数学のようなコースは選択することは可能ですか?
A. 研究生は学位取得を目的とせず半年単位で研究に専念できる制度です。授業の履修はできません(科目によっては聴講を認められる場合があります)。大学院受験対策コースはありません。
Q. 音楽の性質や協和感に興味があり、シラバスに載っている科目のほとんどすべてに興味があるのですが、論文の方向性を絞れずに困っています。
A. 論文の方向性を考えるのも入学前にやっておかなければならないことの一つです。まずは研究対象・研究手法のどちらかを決めると、その先が見えてくるのではないかと思います。
Q. 出願時に提出する研究計画書と試験に出てくる研究計画は同じものを書いていいのでしょうか?
A.ここ数年は、記述試験で「研究計画を書く」というような設問は出していないため、おそらく提出する「研究計画書」とは別のことを書くことになるかと思いますが、現時点で入試に関する具体的なことは回答できません。もし「研究計画について書け」という問題が出れば、研究計画書と同様の内容で記述しても構いません。今までにどのような設問が出ているかは過去問をご確認ください。
Q. 音楽学部を出ていないのですが、音楽の基礎知識を得るための授業を取ろうと思うとかなり忙しくなりますか?
A. 研究に必要となる知識は、大学院でどのような研究を行うかによって決まります。研究に必要であれば、指導教員と相談した上で、学部の授業の一部を受けることも可能です。しかし、研究期間の多くは研究と論文執筆に費やされるものですので、もし専門的な音楽の知識や能力が必要とされる研究をしたいのでしたら、基礎的な知識を一から得るために多くの授業を受けることは難しいとお考えください。必ずしも高度な音楽的知識がなくても実現可能な研究はありますが、その場合でも、当該分野における基礎知識は入学前に身につけておいてください。
Q. アナログシンセサイザーは授業でなくても普段から扱えますか?
A. アナログシンセサイザーが置いてある部屋は学生が自由に使えるわけではありませんが、研究に必要と認められれば使用できる可能性はあります。過去にアナログシンセサイザーの研究をしていた学生が許可を得ていました。